小沢健二/犬は吠えるがキャラバンは進む
あ~お 9月 1st. 2004, 1:57am神様を信じる強さを僕に
というのはこのアルバムのハイライト13分余の大曲‘天使たちのシーン’の一節だけど、このアルバムにはこういう思わず引用したくなるようなフレーズにあふれています。
死んでもかっこ悪いことはしない、という勢いでフリッパーズはありとあらゆる手段で武装して、日本のロックのだささから自由であろうとしていたように思えるのだけど、このアルバムにはそうした力が入った感じがしないのは、小沢健二が自分の音楽に自信がついた証拠なのかなあと思ったりします。
かといっても別にいろんなところから引用するのをやめたわけではないのですが、「それでもこれは僕の音楽」という呟きが聞こえてくる様な音楽というか。実際出来上がった音楽は小沢健二にしか出来ないモノだったわけです。
フリッパーズ時代の口の悪さは有名でした。他のバンドに悪態をついたりして。「日本のロック」の大半はやっぱり欧米のロックへのコンプレックスにまみれてるか、歌謡曲をでっかい音で演奏しているかのどっちかだと思っていた自分には彼らの苛立ちはなんか判る気がしたのです。彼らはありとあらゆる音楽を彼ら独自のセンスで引用しまくることで、そうしたものから抜け出そうとしたのですよね?
初めて聴いた時、フリッパーズの頃より、より内側に入り込んだ歌詞、その一つ一つにはよくある日常的な言葉なのに、フレーズの連なりはとても自分のの心に迫ってきました。意味ありげな謎かけをするのではなく、素晴らしい歌い手がまっすぐに何かを伝えようとしているのが痛いほど伝わってきて、こういう音楽が聴きたかったんだなあと思いました。
このアルバムの『まわりに仲間はいる。大切なひともいる。でもなんというかひとりでもある』という雰囲気と、空間を大切にした音数の少ない演奏はぴったりはまっていいです。凄腕のバック陣の演奏・・・天気読み’のうたいまくるベースとか、‘カウボーイ疾走’のソウルフルなオルガンとかがもう大好きで。全体的にR&Bっぽいのもよいですよね。
それではもう一回、セルフライナーノーツを読みながら‘天使たちのシーン’を聴くとしましょう。旧ジャケにしか入っていない、小沢健二が書いたこの音楽にかけた想いをつづったこの文章が僕はとても好きなのです。
関連する投稿:
タグ: 90's, J-pop, レビュー
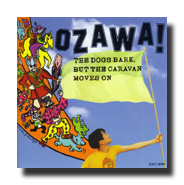

9月 2nd, 2004 at 12:54 AM
小沢健二
この間の夜の科学ライブで小沢健二の「カウボーイ疾走」という曲のカバーを山田さんがしていました。私はゴメスを好きになる前から小沢健二の歌が大好きで、良くこの曲が入…
9月 2nd, 2004 at 12:59 AM
小沢健二
この間の夜の科学ライブで小沢健二の「カウボーイ疾走」という曲のカバーを山田さんがしていました。私はゴメスを好きになる前から小沢健二の歌が大好きで、良くこの曲が入…
9月 2nd, 2004 at 1:06 AM
トラッシュバックをしてみたくてやったんだけど、なぜか2つ重複してしまいましたぁ。ごめんなさいね!しかし、なんでdogsにしちゃったのかな。犬キャラで発売続ければいいのに。。。
9月 3rd, 2004 at 1:54 AM
しゅりーぷさんの記事を読んでこのアルバムを聴きたくなりました。
ライナーノーツを久しぶりに読んだらますます聴きたくなりました。
胸がしめつけられそうな位に感動した大好きなアルバム。
明日、カーステレオでまたいつもより少しボリュームをあげて
じっくりと楽しみながら車を走らせようと思います。
しゅりーぷさん、ありがとう。
9月 3rd, 2004 at 11:15 PM
久々の小沢健二の世界
昨日しゅりーぷさんの記事を読んで聴きたくなったので数年ぶりに小沢健二の『犬は吠えるがキャラバンは進む』を車でかける。小沢健二の声が実に心地よい。私、1stのこの…